アフターコロナを勝ち抜く、繊維カンパニーのビジネス戦略
PRESIDENT INTERVIEW
失敗も含めた多彩な経験が成長の糧に

大学時代に知った商売の難しさ
私の実家は、100名ほどの従業員を抱える関西で1、2位を争う畳屋を経営していました。しかし、私が大学3年の頃に事業を終えることになり、商売や経営の難しさを目の当たりにしたことで、「商売」について学びたいという思いを強くしました。就職活動ではさまざまな業界の企業を訪問し、最終的に伊藤忠商事に巡り合ったのですが、当時私が思い描いていた商売人のイメージに最も近いものを感じたのが、伊藤忠商事の先輩方だったのです。
いざ入社してみると、いくら商売人といってもあくまでも自分たちは商社で働く会社員であるということを痛感。私は事業会社のジョイックスコーポレーションに出向し、社長を務めた経験もありますが、父のように自ら資金繰りをして商いをしていた人間とは大きな差があることを忘れてはいけないと考えています。そうした思いを持ち続けてきたからこそ、岡藤正広社長(当時)のもとで発信されたコーポレートメッセージ「ひとりの商人、無数の使命」は心に響くものがありました。
ブランドビジネスで見た「天国」と「地獄」
これまでで最も印象に残っている仕事は、1994年から携わった「Vivienne Westwood」のビジネスです。若手時代から13年間に及んだこの仕事は、自分の成長の糧になりました。当時は、原宿にいる女子高校生が「Vivienne Westwood」のロゴ入りソックスを履いているような時代で、その後大きなブームとなりました。まだ自分が若かったこともあり、このまま売れ続けると思っていたのですが、そこから売上が急減。一時は最盛期の5分の1にまで落ち込み、会社を辞めなくてはいけないのではないかと思い詰めるほど追い込まれました。ですが、従来の服飾雑貨のライセンスに加え、アパレルのライセンスを取得するために奔走し、ECプラットフォームをつくるなど、さまざまな方たちの協力でビジネスを立て直すことができたのです。
その後も長くブランドビジネスに携わり、時代を牽引してきたデザイナーの方たちとご一緒したり、多くの看板ブランドにも携わったりできました。失敗も含め、消費者に近いところでさまざまな経験ができた私は、とても恵まれていると感じています。だからこそ、若い世代にもいろいろな経験をしてほしいし、そうした機会をつくっていきたいと考えています。
着る喜びを忘れずその道のプロになれ
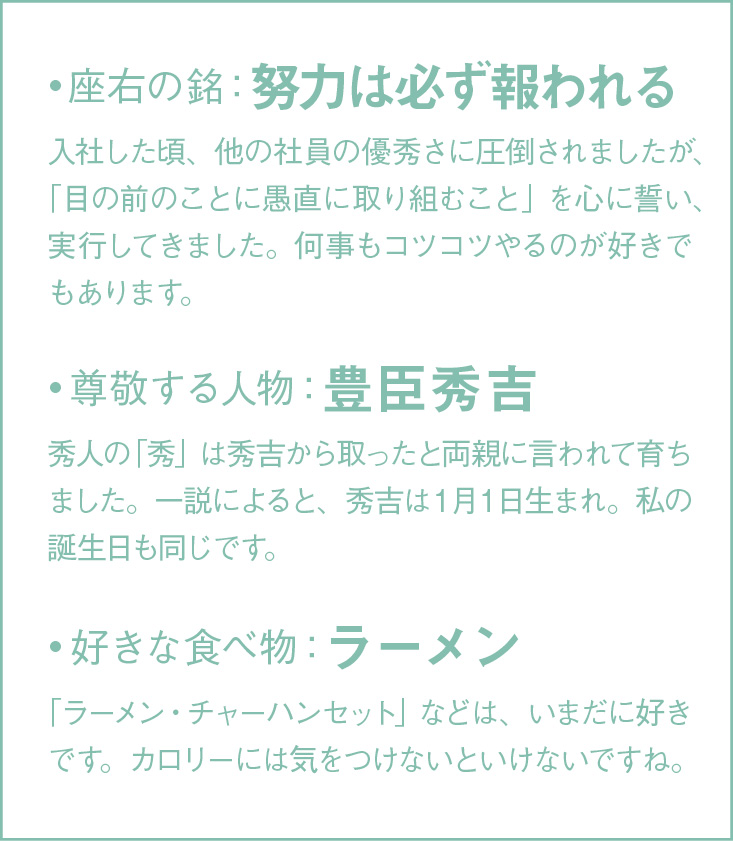
高校、大学時代はDCブームと重なったこともあり、若い頃からファッションが好きで、一時はアルバイトで得たお金の大半を洋服に使っていたほどでした。社会人になってからも、ボーナスが入ると高級スーツをためらいなく買っていた時期がありました。今でも洋服は好きですね。
ジョイックスコーポレーション時代には社員の皆さんと討議をし、企業理念を「着るよろこび、それ以上を」に刷新しました。やはり、着る喜びを知っていることが繊維業界で働く上で何よりも大切なことだと思っています。その上で、「自分に与えられた仕事のプロになること」、「数年先を見据えたビジョンを持つこと」、そして「絶えず明るく前向きに仕事に取り組むこと」。忙しい日々の中で初心を忘れがちになるからこそ、この3つを私自身が意識し続け、同時に若い世代へのメッセージとして伝えたいと思います。
